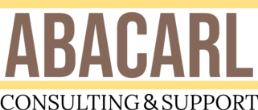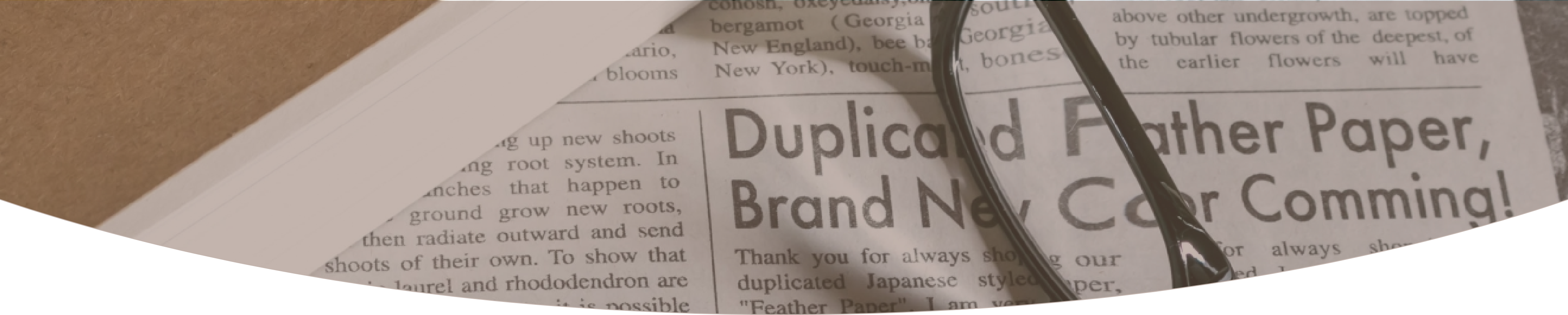2025年4月3日
後継者は家族?従業員?事業承継方法の比較
社長が引退して後継者にバトンを渡すとき、後継者候補にはいくつかの選択肢があります。 大きく分けて、息子や娘などの家族へ引き継ぐ「親族内承継」と、従業員や同業他社など家族以外へ引き継ぐ「第三者承継」に分類されます。 今回は、親族内承継と第三者承継の特徴の違いや、それぞれで生じやすい課題をメリット・デメリットの形で比較します。
親族内承継のメリット
親族内承継のメリットには、一般的に以下のようなものがあります。
1. 経営者の大きな若返りが期待できる
親族内承継では、息子や娘に引き継ぐ場合、経営者の年齢が大幅に若返ることが多く、長期的に安定した経営が可能になります。 一方、従業員に承継する場合は、経験のある従業員が候補となるため、後継者が比較的高齢になり、短期間で再び承継の問題が発生する可能性があります。
2. 株式や資産の承継時に節税対策がしやすい
仮に親から子へ承継を行う場合、法人であれば株式、個人事業であれば事業用資産の承継を行う事になります。
株式や事業用資産は規模によっては、かなり金額の大きなものになり、例えば従業員などの個人に贈与という形で引き継ごうと考えても、大きな贈与税がかかってしまうといった課題があります。
親族内の承継の場合は通常は生前贈与または相続という形を取りますが、この時に各種税制の特例を活用する事で承継時の税負担を軽減出来る場合があります。
3. 従業員や取引先の理解を得やすい
近年、第三者承継が増えていますが、親族への承継は依然として一般的です。 同業他社に売却する場合、従業員は「待遇は維持されるのか」、取引先は「取引が継続できるのか」といった懸念を抱く可能性があります。 親族内承継では、こうした不安が比較的少なく、周囲の理解を得やすいといえます。
親族内承継のデメリット
一方、デメリットについても以下のようなものがあります。
1. 後継者との感情的なトラブルが発生しやすい
社長と後継者という関係以前に当事者は親と子であり、わきまえているつもりでも、やはり社長と従業員という関係とは明確に異なります。
社長が経営上で大事だと考えている事が、後継者からは非合理的・非効率的に見える事もあります。
このように社長と後継者の間で経営方針に相違があると、感情的な衝突に発展する場合が多くあります。
後継者とキチンと向き合って対話する事が非常に大切ですが、この時私たちのような第三者的な立場の人間が調整を行う事で、感情的な衝突を避けて対話をスムーズに進める事が期待出来ます。
仕事で家族との関係が悪くなるのは避けたいと考えると、この点は専門家を活用する大きなメリットになると考えられます。
2. 株式が原因で親族間の相続トラブルになる可能性がある
仮に2人の子供が居て、その内の1人を後継者に選定したとしましょう。
通常、事業承継では承継後の安定的な経営のために、株式は後継者に集中的に承継させる事が望ましいです。
しかし、後継者のみに株式を承継させようとすると後継者以外の親族には不公平感が生まれます。
社長が存命の間は表面化しなくても、亡くなられて相続というタイミングで大きな問題になる事もあります。
※相続発生時には生前に贈与された財産も加味して遺産分割が行われます。興味のある方は「特別受益」や「遺留分」で検索をしてみてください。
会社を後継者だけに相続させる場合、法的・感情的なリスクに配慮が必要で、専門家と相談しながら進める事が大切になります。
3. 後継者に経営者としての実力が不足している場合がある
親族内承継では後継者候補の数が限定的になり、必ずしも経営者としての適性や実力が備わった人物がいるとは限りません。
生来の性格などで向き不向きはあるかもしれませんが、適切な教育を行う事で経営者としての能力を育てる事は可能です。
親族内承継では後継者教育を行う時間的余裕が多い傾向があるので、放任ではなく適切に教育を行っていく事が大切になります。
以上が親族内承継の主なメリット・デメリットになります。
同様の解説を行っている情報源は沢山ありますが、今回は特に家族の関係などに関するリスクに注目して記載いたしました。
家族の関係が悪くなってほしいと考える人は居ないと思いますが、結果的に事業承継をきっかけにそのような事態になる事は少なくありません。
親族内承継に潜んでいる確かなリスクなので、これらを認識した上で事業承継に向き合う事が大切になります。
第三者承継(M&A・従業員承継)のメリット
次に第三者承継のメリットを見ていきましょう。親族内承継と比較してどのような違いがあるでしょうか。
1. 家族に後継者がいなくても会社を存続できる
子供が居たとしても全く異なる仕事をしており、後継者になって欲しいと相談しても明確に断られる事もあります。
ここで廃業という選択肢を取ると従業員の雇用が失われ、取引先に対しても影響が出るため、関係各所に「申し訳ない」と挨拶周りをされる方もいらっしゃいます。
第三者承継では同業他社や、新規事業の展開を検討している会社なども後継者候補となります。
M&Aと聞くと大規模な会社が行うイメージがあるかもしれませんが、現在は昔に比べて小規模なM&Aが盛んに行われており、現実的な選択肢となっています。
2. 売却益を得ることができる
会社を売却する事で、目に見えない会社の強みなども含めて現金化する事が可能です。
売却で得た現金を引退後の楽しみや新しい挑戦に使ってみるのも良いかもしれません。
また将来的にお子さんに財産を相続される場合も、相続した現金から相続税を払う事が可能となるので、相続税対策としても有効と考えられます。
3. 意欲的な後継者に引き継ぐことができる
後継者候補が限定されないので、自社の理念を理解してくれたり、成長に意欲的な後継者への承継が可能です。
実際にM&Aで売却を検討する場合、まずは社名を伏せた状態で買い手候補を探し、その後代表者同士の面談を行うなど、相手の顔を見て売却先をじっくりと検討する事が出来ます。
第三者承継のデメリット
一方、第三者承継には以下のようなデメリットもあります。
1.適切な買い手を見つけるのに時間がかかる事がある
買い手候補の選択肢が限定されないだけに、よりよい買い手を探そうとして、なかなか売却に踏み切れない事があります。
また、買い手候補も、最初は限定的な情報をもとにアプローチをしてくるので、詳細な情報を開示した段階で買い手候補の期待と一致せずに取りやめとなる事も多くあります。
2.企業文化や経営方針の違いによる混乱
M&Aの場合、新たな経営陣によって企業文化や経営方針が大きく変わる可能性があり、従業員の不安や取引先との関係悪化を招くこともあります。
また取引先との契約にはチェンジオブコントロール(COC条項)という、経営者が変わる事で取引条件が白紙になるといった内容が盛り込まれている事もあり
主要取引先との契約が継続できないと事業が成り立たない場合には売却が難しくなるケースもあります。
3.売却後のトラブル
売却時には買い手の責任でデューディリジェンスという資産調査が行われる事が一般的です。
しかし、その調査も完全なものではないので、最終的な契約時には「表明保証」を求められる事が一般的です。
表明保証は従業員への過去の残業代未払いや法的なリスク(パワハラ等)など隠れた問題がないかを保証するものです。
売却後にこのような問題が発覚した場合、責任の所在や賠償について協議が必要となります。
4.従業員承継の場合は資金調達が難しい
従業員や役員に承継を行う場合、後継者が株式を買い取る形を取る場合があります。
この時、後継者は個人になるため株式の購入代金を調達するのが難しい事が多いです。
金融機関から借り入れを行って購入代金を用意するケースやファンドの協力を得るケースがありますが、いずれにせよ株式の取得費用の調達は課題となります。
いかがでしょうか?おおまかにではありますが親族内承継と第三者承継のメリットなどについてご説明しました。
どのような手法を取る場合でも事業承継では考えなければいけない課題やリスクが多く存在します。
事業承継がきっかけで経営に支障が出たり、加速関係の悪化を招かないように入念に準備をして進めましょう。